
この記事の目次(クリックでジャンプ)
1. はじめに:インフルエンサー時代の甘美な誘い文句
ソーシャルメディアが現代社会に深く浸透し、オンライン上のパーソナリティであるインフルエンサーの影響力は増大の一途を辿っています。彼らは、ファッション、美容、ライフスタイルなど、多岐にわたる分野でトレンドを牽引し、消費者の行動を左右する存在です。その影響力の大きさゆえに、近年では、フォロワーに対し「100%儲かる」といった甘美な言葉で、現実離れした利益を約束するインフルエンサーが後を絶ちません。
「簡単にお金持ちになれる」、「リスクなしで確実に稼げる」といった魅力的な謳い文句は、経済的な自由を求める人々や、手軽に収入を増やしたいと考える層の心理に強く訴えかけます。特に、現代社会における経済的な不安感や、ソーシャルメディアで目にする華やかなライフスタイルへの憧れは、こうした誘惑に乗りやすい土壌を作り出しています。
しかし、これらの「絶対儲かる」という約束の裏には、巧妙に仕組まれた罠や、法的なグレーゾーンを突いた危険なスキームが潜んでいる可能性が高いことを認識する必要があります。本稿では、読者の皆様がインフルエンサーによる過剰な宣伝に惑わされることなく、冷静にその実態を見抜けるよう、彼らが用いる欺瞞的な手口を詳細に解説します。さらに、これらの行為が触れる可能性のある法的問題点や、消費者が身を守るために取るべき具体的な対策についても深く掘り下げていきます。ソーシャルメディアの世界で蔓延する甘い誘惑の裏に隠された真実を明らかにし、賢明な判断を下すための一助となることを目指します。
2. 巧妙な手口を暴く:「100%儲かる」インフルエンサーの暗躍
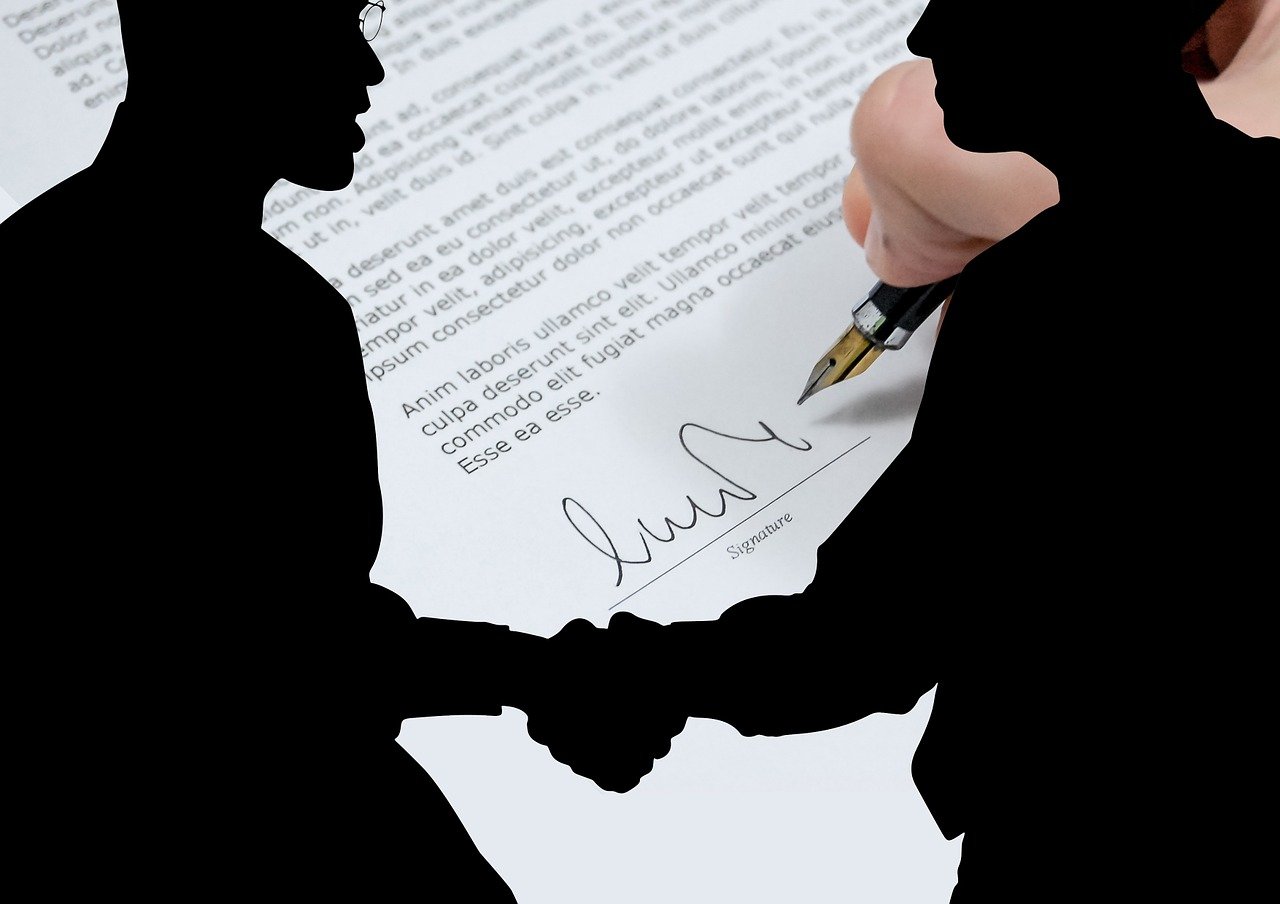
「100%儲かる」と謳うインフルエンサーは、様々な手法を駆使してフォロワーを誘い込みます。その多くは、手軽さや即効性を強調し、あたかも誰でも簡単に大金を稼げるかのような錯覚を抱かせようとします。
まず、「手軽な収入」という幻想を植え付ける手口が挙げられます。例えば、SNS上で「動画にいいねをするだけで1日に5,000円から5万円稼げる」といった副業詐欺の勧誘事例が報告されています(1)。これは、最初は簡単なタスクと少額の報酬で信用させ、最終的には高額な費用を要求する手口へと発展することが多く、安易に高収入が得られるという誤った認識を植え付けます。
また、「#副業」「#お金」「#お小遣い稼ぎ」といったハッシュタグを利用して副収入に関心のある人々を集め、「登録すれば〇〇万円以上は確実に稼げる」などと謳い、システム利用料や高額な資料の購入を促す事例も確認されています(2)。あたかも簡単な作業で誰でも高収入を得られるかのように装うことで、警戒心を解き、次の段階へと誘導しようとする意図が見られます。
さらに、「必ず儲かる投資がある」と持ちかけ、元金を預ければ増やして返すと約束し、専用サイトのサーバー代や登録料といった名目で高額な金銭を要求する副業詐欺も存在します(3)。このように、初期段階では「簡単」「手軽」といったキーワードで関心を引きつけ、最終的には金銭的な負担を強いるのが常套手段と言えるでしょう。
次に、限定性や希少性を強調し、フォロワーの焦燥感を煽る手法も頻繁に用いられます。「今だけ」「あなただけ」「限定〇〇名」といった言葉を使い、あたかも特別な機会であるかのように見せかけ、冷静な判断を鈍らせようとします。また、成功者のイメージを誇示することで、フォロワーに夢を見させる手法も一般的です。豪華な食事、高級ブランド品、海外旅行など、華やかなライフスタイルをSNSに投稿し、「これも全て投資や副業で手に入れたものだ」とアピールします。あたかも自分も同じようにすれば成功できるのではないかという期待感を抱かせ、提供する情報商材や投資案件への関心を高めようとします。
しかし、これらの成功例は誇張されているか、あるいは一部の幸運なケースに過ぎない可能性が高いことに注意が必要です。さらに、巧妙な手口として、ピラミッドスキームやポンジ・スキームへの勧誘も存在します。ポンジ・スキームは、「元本保証」「高利回り」といった謳い文句で出資を募り、実際には運用益ではなく、後から参加した出資者の資金を配当金として支払うことで、あたかも利益が出ているかのように装う詐欺の手法です(4)。初期の参加者には実際に配当金が支払われるため信用しやすいのですが、最終的には資金を持ち逃げされるケースがほとんどです。このようなスキームは、新たな参加者の勧誘が不可欠であり、紹介料を支払うことで参加者を増やそうとする特徴があります(5)。
また、情報商材の販売も、「100%儲かる」と謳うインフルエンサーの主要な収入源の一つです。これらは、高額なe-book、オンラインコース、秘密のノウハウといった形で販売され、「誰でも簡単に稼げる方法」が教えられていると謳われます(8)。しかし、その内容は一般的な知識の寄せ集めであったり、実践しても全く効果が得られないものであったりすることが少なくありません(9)。インフルエンサー自身の成功体験を誇張したり、再現性の低い特殊な事例をあたかも普遍的な法則であるかのように語ったりすることで、購入者を信用させようとします。実際には、情報商材の購入者のほとんどが約束されたかのような利益を得ることはなく、インフルエンサーだけが利益を得るという構造になっています。
さらに、「ポンプ・アンド・ダンプ」と呼ばれる手法も存在します。これは、インフルエンサーが自身のフォロワーに対し、特定のあまり知られていない金融商品(例えば、投機的な暗号資産など)を推奨し、大量に購入させることで価格を人工的に吊り上げます。その後、価格が上昇したところで、インフルエンサー自身は保有していた商品を売り抜け、利益を得ます。しかし、後に残されたフォロワーは、価格が急落した後に金銭的損失を被ることになります。インフルエンサーの影響力を利用して市場を操作し、自身の利益を優先する悪質な手口と言えるでしょう。
3. 法的綱渡り:「絶対儲かる」の裏に潜むグレーゾーンと違反の可能性

「100%儲かる」と謳うインフルエンサーの行為は、一見すると魅力的に映る一方で、法的な観点からは多くのグレーゾーンや潜在的な違反行為を含んでいます。
まず、アフィリエイトマーケティングと欺瞞的な行為の線引きは曖昧になりがちです。正当なアフィリエイトマーケティングは、インフルエンサーが企業の商品やサービスを宣伝し、その成果に応じて報酬を得るという仕組みですが、その際にスポンサーシップを適切に開示することが求められます。しかし、「100%儲かる」と謳うインフルエンサーの中には、報酬を得ているにもかかわらず、あたかも個人的な推奨であるかのように装い、広告であることを隠蔽するケースが見られます(14)。これは「ステルスマーケティング(ステマ)」と呼ばれ、消費者の自主的かつ合理的な選択を阻害する不当な行為とみなされる可能性があります。
実際に、健康食品のステルスマーケティングを行ったとして、大手製薬会社が消費者庁から措置命令を受けた事例も存在します(15)。この事例では、インフルエンサーがインスタグラムでサプリメントを宣伝した際、「PR」表記があったものの、その投稿を自社のオンラインショップに転載した際に広告表示を欠いたため、消費者を誤認させる表示であると判断されました。
ステルスマーケティングの手口は多様であり、従業員が一般消費者を装ったり、インフルエンサーに報酬を支払って広告であることを隠してレビューを投稿させたり、商品やサービスを無償提供して好意的な口コミを誘導したりするケースなどが報告されています(16)。近年、ステルスマーケティングに対する規制は強化されており、広告であることを明確に表示することが重要となっています(18)。ただし、インフルエンサーの中には、規制に対する認識不足から、企業からの依頼がない投稿にまで自主的に#PRを付けてしまうケースも見られ、その線引きの難しさが伺えます(28)。
「100%儲かる」という誇大広告も、景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)に抵触する可能性があります。この法律は、商品やサービスの品質、規格、その他の内容について、実際のものよりも著しく優良であると表示したり、事実に反して競争事業者のものよりも著しく優良であると表示したりする「優良誤認表示」を禁じています(29)。根拠のない「絶対儲かる」という保証は、消費者に誤解を与え、不当な顧客誘引につながる可能性があります。
消費者庁は、誇大広告に該当するかどうかを判断するために、表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができ、提出されない場合は不当表示とみなされます(29)。特に、健康食品や美容関連の商品においては、効果効能に関する誇大広告が問題視されることが多く(34)、「〇ヶ月で痩せる」「シミが消える」といった具体的な効果を謳う場合は、科学的根拠が必要となります。誇大広告を見抜くためには、「保証」「絶対」といった断定的な言葉や、具体的な根拠が示されていない情報に警戒することが重要です(34)。
さらに、「100%儲かる」スキームが金融商品への投資を伴う場合、金融商品取引法に抵触する可能性も高まります。未登録の業者が投資勧誘を行ったり、元本保証や確実な利益を謳ったりする行為は、同法で禁じられています(4)。SNSを通じて著名人や投資家を装い、偽の投資広告で誘い込み、言葉巧みに信用を得て金銭を騙し取る手口が多発しており(39)、「必ず儲かる」「あなただけ」といった甘い言葉には特に注意が必要です(39)。金融商品取引法に違反した場合、刑事罰や行政処分が科される可能性があり、インフルエンサー自身も法的責任を問われることがあります(49)。
消費者庁や国民生活センターなどの消費者保護機関は、こうした悪質な手口に対して積極的に注意喚起を行っています(55)。SNS広告やダイレクトメッセージから誘導される詐欺、無料体験をきっかけとした高額契約の勧誘など、具体的な事例を公表し、消費者に警戒を呼びかけています。これらの機関は、怪しい儲け話や投資トラブルに関する相談窓口も設けており(65)、消費者が被害に遭わないための情報提供や、被害に遭った場合のサポートを行っています。
4. 実例に見る問題点:インフルエンサープロモーションの落とし穴

インフルエンサーによる「100%儲かる」という宣伝には、実際に多くの問題が生じています。具体的な事例を見ることで、その危険性をより深く理解することができます。
近年、暗号資産(仮想通貨)市場の変動を利用し、特定のあまり知られていないコインをインフルエンサーがこぞって推奨した結果、一時的に価格が高騰したものの、その後暴落し、多くのフォロワーが損失を被った事例が報告されています。インフルエンサー自身は高騰時に売り抜けて利益を得ていたものの、後に残されたフォロワーは価値のないコインを抱えることになりました。
また、高額な情報商材を販売するインフルエンサーの中には、自身の過去の成功体験を誇張したり、限定的な事例を一般化したりするケースが見られます。例えば、「〇ヶ月で〇〇万円稼いだ秘密の方法」といった情報商材を販売しても、購入者のほとんどが約束されたかのような成果を上げることはなく、多額の費用だけが残るというトラブルが多発しています(9)。
大正製薬株式会社が健康サプリメント「NMNtaisho」の販売促進において、インフルエンサーに広告を依頼した際、その投稿を自社サイトに転載した際に広告表示を怠り、ステルスマーケティングと認定された事例は、法的な問題点を示す好例です(15)。インフルエンサーの投稿自体には「PR」との記載があったものの、自社サイトへの転載時にそれが削除されたため、消費者は第三者の意見と誤認しやすくなり、景品表示法違反と判断されました。
同様に、RIZAP株式会社(chocoZAP)も、インフルエンサーのインスタグラム投稿を、あたかも顧客の声であるかのように自社サイトに掲載し、ステルスマーケティングとして消費者庁から措置命令を受けています(21)。これらの事例は、企業がインフルエンサーマーケティングを行う際に、透明性を確保し、消費者を誤解させることのないよう、細心の注意を払う必要があることを示唆しています。
5. 消費者への警鐘:「甘すぎる誘い」に潜む危険な兆候

「100%儲かる」というインフルエンサーの誘いには、注意すべき危険な兆候がいくつか存在します。これらの兆候を認識することで、詐欺や不当なスキームに巻き込まれるリスクを減らすことができます。
まず、「リスクなしで必ず儲かる」といった非現実的な約束は、最も警戒すべきサインです(3)。投資やビジネスの世界において、リスクを伴わない確実な利益は存在しないと言っても過言ではありません。もしそのような誘いを受けた場合は、まず疑うべきでしょう。
また、「今すぐ行動しなければならない」といった強いプレッシャーをかけてくる場合も注意が必要です(6)。冷静に検討する時間を与えず、即決を迫るような手法は、消費者を欺くための常套手段です。さらに、ビジネスモデルや投資スキームの透明性が低い場合も警戒が必要です。具体的な仕組みやリスクについて明確な説明を避けたり、複雑な専門用語で煙に巻こうとしたりする場合は、何か隠している可能性があると考えられます。
高額な初期費用や不透明な手数料を要求するスキームも危険です(2)。情報商材の購入、システムの利用料、会員登録料など、様々な名目で金銭を要求し、その後のリターンが保証されないケースが多く見られます。成功者の体験談が誇張されている、あるいは具体的な証拠が示されない場合も注意が必要です。SNSに投稿された華やかなライフスタイルや、信憑性の低い収益のスクリーンショットだけを鵜呑みにするのは危険です。
6. 身を守るために:インフルエンサーとの賢い付き合い方

インフルエンサーの情報を鵜呑みにせず、自ら情報を精査し、冷静な判断を下すことが重要です。まず、インフルエンサーが推奨する金融商品やビジネスに関する情報を、必ず自分自身で調査しましょう。関連する企業の評判、過去の実績、リスクなどを多角的に確認することが大切です。
「必ず儲かる」といった保証には懐疑的になりましょう。金融商品やビジネスには常にリスクが伴うことを忘れてはなりません。即断を避け、時間をかけて慎重に検討しましょう。焦って判断すると、後悔する可能性が高くなります。
少しでも怪しいと感じたら、独立した第三者(例えば、金融機関の専門家や消費者センターなど)に相談することも有効な手段です(65)。不審な勧誘や詐欺の疑いがある場合は、迷わず関係機関に通報しましょう。情報提供が、他の被害者を防ぐことにつながる可能性があります。
消費者保護に関する基本的な法律や規制について、ある程度の知識を持っておくことも、自己防衛のために役立ちます。
7. 結論:甘い誘惑に惑わされず、賢い消費者であれ

本稿では、「100%儲かる」と謳うインフルエンサーの背後に潜む欺瞞的な手口と、それに伴う法的リスクについて詳細に解説してきました。彼らは、手軽な収入の幻想、限定性の強調、成功者のイメージの誇示など、様々な手法を用いてフォロワーを誘い込み、最終的には金銭的損失をもたらす可能性のあるスキームへと誘導します。これらの行為は、ステルスマーケティング、誇大広告、未登録業者による金融商品取引など、様々な法的問題を含む可能性があります。
消費者庁や国民生活センターは、こうした悪質な事例に対して注意喚起を行い、消費者の保護に努めていますが、最終的に身を守るのは消費者自身です。「必ず儲かる」という甘い誘惑には、常にリスクが伴うことを肝に銘じ、インフルエンサーの言葉を鵜呑みにするのではなく、自ら情報を精査し、冷静な判断を下すことが不可欠です。
独立した調査、専門家への相談、そして消費者保護に関する知識を持つことが、危険なスキームから身を守るための重要な鍵となります。真の金銭的成功は、安易な約束ではなく、努力、知識、そして賢明な判断によって築かれるものであることを忘れてはなりません。
表1: インフルエンサー広告に関する日本の主要な法的概念の概要
| 法的概念(日本語名) | 簡単な定義/説明 | 主要な規制機関 | 違反した場合の潜在的な結果 | 「100%儲かる」スキームとの関連性 |
|---|---|---|---|---|
| ステルスマーケティング | 広告であることを隠して行われる宣伝行為 | 消費者庁 | 措置命令、課徴金、社会的信用失墜 | 報酬を得ているにもかかわらず広告と開示せずに「100%儲かる」スキームを推奨 |
| 景品表示法 | 不当な景品類の提供や、商品の品質・価格等で消費者を誤認させる表示を禁止 | 消費者庁 | 措置命令、課徴金、罰金、懲役 | 根拠のない「必ず儲かる」という保証や過剰な優良性を強調 |
| 金融商品取引法 | 金融商品の販売・勧誘、投資助言などに関する規制を定める法律 | 金融庁 | 刑事罰(罰金、懲役)、行政処分(業務停止命令など) | 未登録業者による投資勧誘や、元本保証・高利回りを謳う行為 |
| 優良誤認表示 | 実際よりも著しく品質が良いと誤認させる表示 | 消費者庁 | 景品表示法に準ずる | 「100%儲かる」という強調表示に根拠がない場合、優良誤認とみなされる可能性 |
| 誇大広告 / 虚偽広告 | 事実と異なる、または大幅に誇張された広告表示 | 消費者庁 ほか | 各法律に準ずる罰則・措置 | 根拠のない「絶対」「確実」などの断定的表現が問題視される |
以上が「100%儲かる」と声高に叫ぶインフルエンサーたちの実態と、それを取り巻く危険なグレーゾーンの全容です。華やかなSNSの投稿や甘い誘い文句に惑わされることなく、しっかりとリスクを見極めて、安全で健全な情報収集と行動を心がけましょう。
💬 あなたの体験や意見を聞かせてください!
感想・リクエスト・タレコミ、大歓迎!
下の送信ボタンから、あなたの意見をぜひお寄せください。
🎁 今ならもれなく3大プレゼント! 🎁
- 💡 「最新詐欺手口&対策リスト(2025年版)」
👉 急増する詐欺の手口と回避策を、わかりやすく解説! - 💰 「知らなきゃ損!政府の補助金&助成金リスト」
👉 住宅・子育て・医療・教育…今すぐ使えるお金をチェック! - 🏦 「銀行・クレジットカードの隠れ手数料一覧」
👉 知らずに払ってる手数料、サクッと削減する方法を伝授!
👇 あなたの一言が、新たな情報発信のヒントに!
今すぐ送信して、プレゼントをGET🎁✨







