
この記事の目次(クリックでジャンプ)
1. 事件の概要
ジュビリーエース(Jubilee Ace)事件は、暗号資産(仮想通貨)への高利回り投資をうたった大規模な出資詐欺事件です。2019年頃から国際的な「ジュビリーグループ」が運営する投資商品「ジュビリーエース」や後継の「ジェンコ(JENCO)」「GTR」への出資が日本国内で広まりました。運営者たちは「暗号資産の取引所間の価格差を突く自動取引で利益を生む」「月利10~20%の高配当」「保険会社が元本保証」などとうたい、ビットコインなど仮想通貨での出資を募りました。全国でセミナーやオンライン勧誘が行われ、主に20~30代を中心に 10万件以上の契約・総額約650億円相当の暗号資産が集められたとされています。しかし実態は新規出資金で配当を装うポンジ・スキーム(ねずみ講)であり、2020年末頃から出金不能となって破綻、最終的に主要メンバーが逮捕される事態となりました。
2. 時系列順の経緯
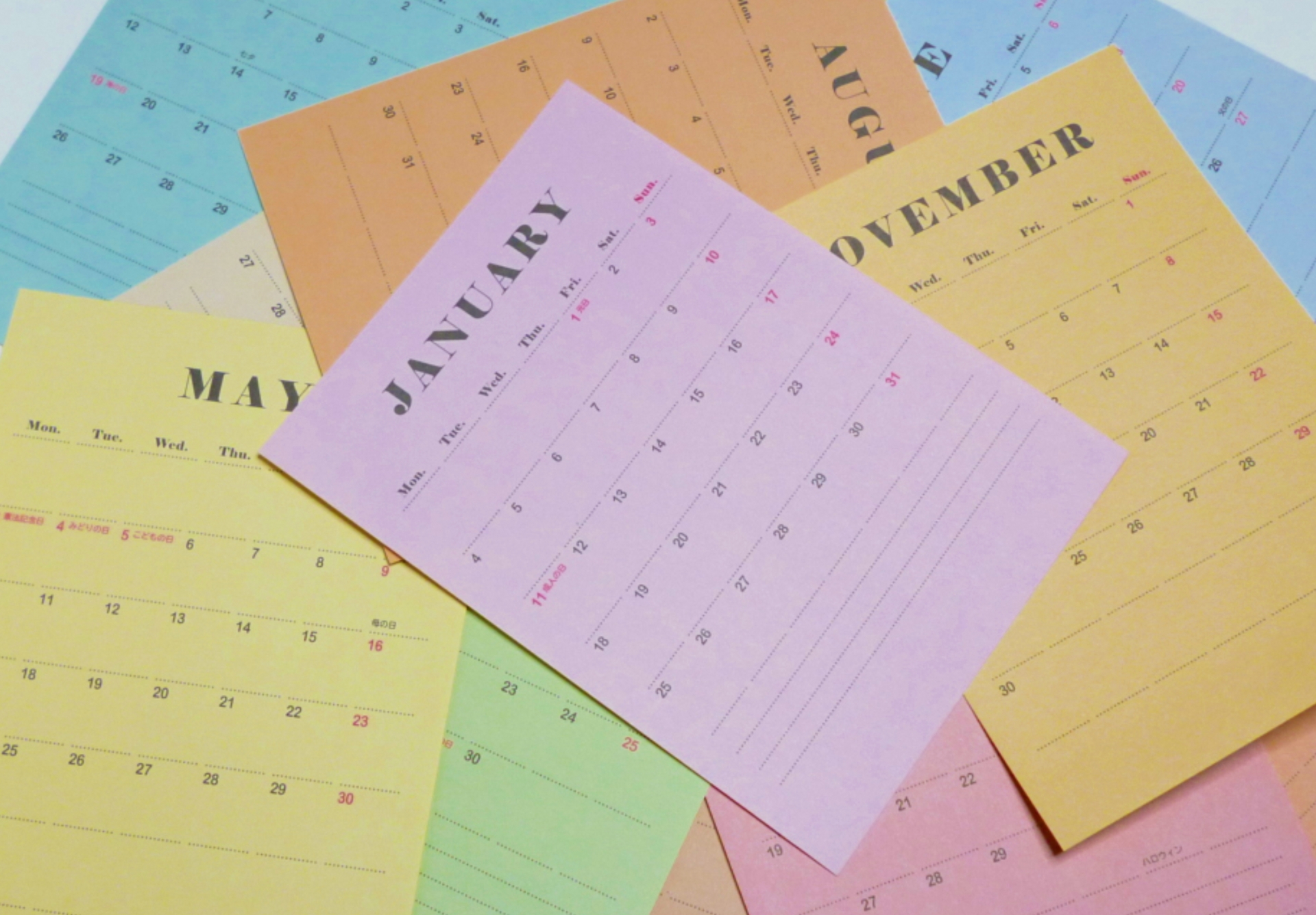
主要な経緯を時系列で示します。
| 時期 | 出来事 |
|---|---|
| 2018年 | 海外でジュビリーエース社が設立(英領ヴァージン諸島に登記と称する)。独自の「AQUAシステム」による暗号資産・スポーツ・コモディティの裁定取引(アービトラージ)サービス開始を謳う。※ |
| 2019年4月頃 | 日本国内で出資勧誘開始 |
| 2019年11月 | ハワイで世界大会イベントを開催するなど事業拡大を演出(世界各国から500名超参加と宣伝)。※ |
| 2020年5月 | 日本で改正金融商品取引法施行、暗号資産による出資もファンド規制の対象となる(無登録での勧誘が違法化) |
| 2020年頃 | 投資商品名を「ジェンコ(JENCO)」などに変更し出資継続(ジュビリーエースから移行)。月利20%など高配当・元本保証を引き続き宣伝 |
| 2020年11月 | 出資者が出金できないトラブルが相次ぎ発生。以降、配当停止・連絡不能となり実質的に運用破綻 |
| 2021年夏 | 出資金の返還を求める被害相談が警視庁に寄せられる |
| 2021年11月9日 | 警視庁が主犯の玉井暁容疑者(当時53歳)ら男女7人を金融商品取引法違反(無登録営業)容疑で一斉逮捕 |
| 2022年 | 玉井被告に執行猶予付き有罪判決が確定 |
| 2023年1月 | 東京国税局が玉井元被告の巨額な所得隠しを把握。未納所得税約24億円に対し、警視庁押収済みの現金約2億円を差し押さえ |
| 2023年5月 | ジュビリーエース事件の元関与者が、新たな暗号資産投資詐欺「マーケットピーク」事件でも勧誘に関与し再逮捕される。(大型投資詐欺が形を変えて繰り返されている) |
※海外登記や「AQUAシステム」による裁定取引の詳細は会社側発表によるもので、信ぴょう性は確認されていません。
上述の通り、事件は2019年から急拡大し、2020年末に崩壊、翌2021年に捜査・摘発という流れでした。摘発後の2022年に刑事裁判が行われ、有罪判決が出たものの執行猶予付きで実刑は免れています。2023年には税務当局による資産没収や、事件関与者が別の投資詐欺で再逮捕される動きもあり、事件は現在も後を引いています。
3. 会社の概要と事業内容

ジュビリーエース社は自称・海外(英領ヴァージン諸島)登記のフィンテック企業で、表向きの事業内容は暗号資産やスポーツ等の裁定取引(アービトラージ)による資産運用でした。公式には2018年創業、資本金5,000万ドル規模とうたわれ、独自の「AQUAプラットフォーム」と称する高速取引システムで仮想通貨・スポーツベッティング・コモディティの価格差を利用した低リスク収益を上げると宣伝していました。実際の運用プロセスとしては、出資希望者が専用のウェブサイトからビットコインなど暗号資産を送金して口座開設し、その残高に応じて日利0.1~1%前後(月利換算で数~20%以上)の配当が付与される仕組みでした。出資コースは段階別に設定され、例えば1口1,000ドル相当から数万ドル単位のパッケージを購入するとそれに応じた“ジュビリークレジット”が与えられ、運用を預けると高利回りが得られるとうたっていました。配当は暗号資産で日々口座に計上され、いつでも出金できるとうたわれていました。
ジュビリーエース社自体は金融商品取引業等の日本の登録は一切なく、日本法人も未設置でした。勧誘時には「海外に本社がありグローバルに展開」「日本の金融庁登録が無いのは海外事業だから問題ない」と説明されるケースもありました。しかし実際には、この会社の実態は投資運用実績のないペーパーカンパニーに過ぎず、金融庁等の監督を逃れるために日本国内では正式な会社組織を置かず、水面下でマルチまがい商法のネットワークを組織していたとみられます。勧誘時には「Jubilee Group」という名称も使われ、ジュビリーエースおよび後継商品(ジェンコ、GTRなど)は同グループ傘下の投資運用会社という位置付けで宣伝されていました。要するに、表向きは高度なアルゴリズム取引を行う国際投資企業を装いながら、内情は無登録のまま資金集めだけを行う実体不明の投資グループだったのです。
4. 実際には運用実態がなかった点

ジュビリーエースは名ばかりの投資事業で、実際にはまともな運用実態がなかったことが摘発により明らかになりました。警視庁の調べによれば、同グループは宣伝していたような安定した高配当を生み出す運用を行っておらず、約束した配当金を支払わずに出資者からの返金要求を逃れようとしていたとされています。2020年末以降、出資者が口座から仮想通貨を引き出せなくなった時点で実質的に破綻が露呈し、その後運営側は「日本での金融ライセンス未取得」を理由に出金停止を正当化しようとしたり、出資金を別の新しいシステムへ振り替えさせるなどの時間稼ぎを行いましたが、どれも配当は支払われず終わりました。
運営側の資金管理は極めて不透明で、出資金は暗号資産で受け付けつつも一部では勧誘者が現金で直接預かったケースも判明しています。にもかかわらず領収書や正式な契約書は一切発行されず、「マネーロンダリング対策のため」などともっともらしい理由を付けて証拠を残さないようにしていました。こうした状況から、当初より実際に資金を運用して増やす意思はなく、資金を集めて流出させること自体が目的だった可能性が高いです。事実、捜査段階で押収された現金はごく一部(約2億円)に留まり、集められた暗号資産の大半は既に海外に送金される等して流出済みで返金は困難な状況と報じられました。また、後述のように主犯格の男は巨額の所得を申告せず私的流用していた形跡があり、集めた資金を運用に充てていたとは到底考えられません。以上より、ジュビリーエースには実質的な資産運用の実体が最初から存在せず、出資金は配当に見せかけて一部を返す以外は組織内で消費・分配されていたと考えられます。
5. ポンジ・スキームと認定された経緯

ジュビリーエースは、その高配当の仕組みや配当停止の顛末から典型的なポンジ・スキーム(ねずみ講的詐欺)と認定されています。運営当初から自転車操業的に新規出資金を既存出資者への配当に充てる構造であり、出資の拡大が止まれば配当維持が不可能になる仕組みでした。実際、2020年11月に出資金引き出し不能が相次いだことで破綻が表面化し、この時点で多くの出資者が詐欺に気付くことになりました。警視庁も捜査の結果、本件を「高利回り配当を謳った無登録の出資詐欺事件」と位置付けており、金融商品取引法違反での立件に踏み切っています。報道でも「650億円規模の暗号資産ねずみ講事件」「空前の被害を出した凶悪なマルチ詐欺事件」として伝えられ、被害の深刻さから社会問題視されました。
逮捕後の捜査・公判でも、事業実態の無さが浮き彫りになっています。グループは当局に無登録であったことから金融商品取引法違反に問われましたが、詐欺罪での立件こそされなかったものの、その手口と被害状況から実質的にポンジ・スキーム型の詐欺であったことは明白です。専門家も「昨年5月の法改正で暗号資産も規制対象になったことで玉井容疑者の逮捕に至った。ただ刑罰は軽く、彼のような“マルチの帝王”はまた次の標的を定めているだろう」と指摘しており、法的にも社会的にも本件が悪質なねずみ講型投資詐欺と認定されるに至っています。警察発表でも「暗号資産で全国から650億円相当を集めた」「高利配当をうたった出資金詐取事件」としており、これが単なる違法営業ではなく出資金自転車操業の詐欺スキームだったことが公式に認められた形です。
6. 社会的な影響

本事件は金銭被害のみならず、被害者の人生に深刻な影響を及ぼしました。その象徴的な例が、当時22歳の女性Aさん(仮名)が投資被害を苦に自殺した痛ましい事例です。Aさんは2020年秋、新社会人になった矢先に大学時代の同級生からジュビリーエースへの投資を勧誘されました。将来への不安もありわずか1か月足らずの間に約150万円を出資しましたが、出資後まもなく配当金の引き出しができなくなり、返金の見込みも立たない状況に追い詰められました。絶望したAさんは2020年10月に自ら命を絶ってしまい、若い命が失われるという最悪の結果を招いています。Aさんの無念を晴らすべく遺族(母親)は勧誘を行った同級生やグループ関係者3名を相手取り損害賠償訴訟を提起しました。遺族は「他の被害者も助けたい」と訴え、詐欺加担者の責任を問うとともに再発防止を社会に訴えています。
この他にも、表面化していないだけで精神的・経済的に深刻な打撃を受けた被害者は多数存在するとみられます。特に若年層で投資経験の乏しい被害者が多く、消費者金融から借金をしてまで出資し多重債務に陥ったケースも少なくありません。650億円もの巨額資金が消えたことで、住宅ローンや学費に充てるはずだった貯金を失った家計、老後資金を失った高齢者など、それぞれの人生設計に大きな狂いが生じました。被害者の中には泣き寝入りせずに弁護士や警察に相談したり、被害者同士で情報共有して返金を模索する動きもあります。しかし加害者グループの摘発後も資金回収は進んでおらず、多くの被害者が経済的損失と精神的苦痛を抱えたままです。この事件は、投資詐欺が人命を奪い得ること、そして若者層にも大きな被害を及ぼしたことから、社会に大きな衝撃と教訓を与えました。
7. 勧誘手口の詳細
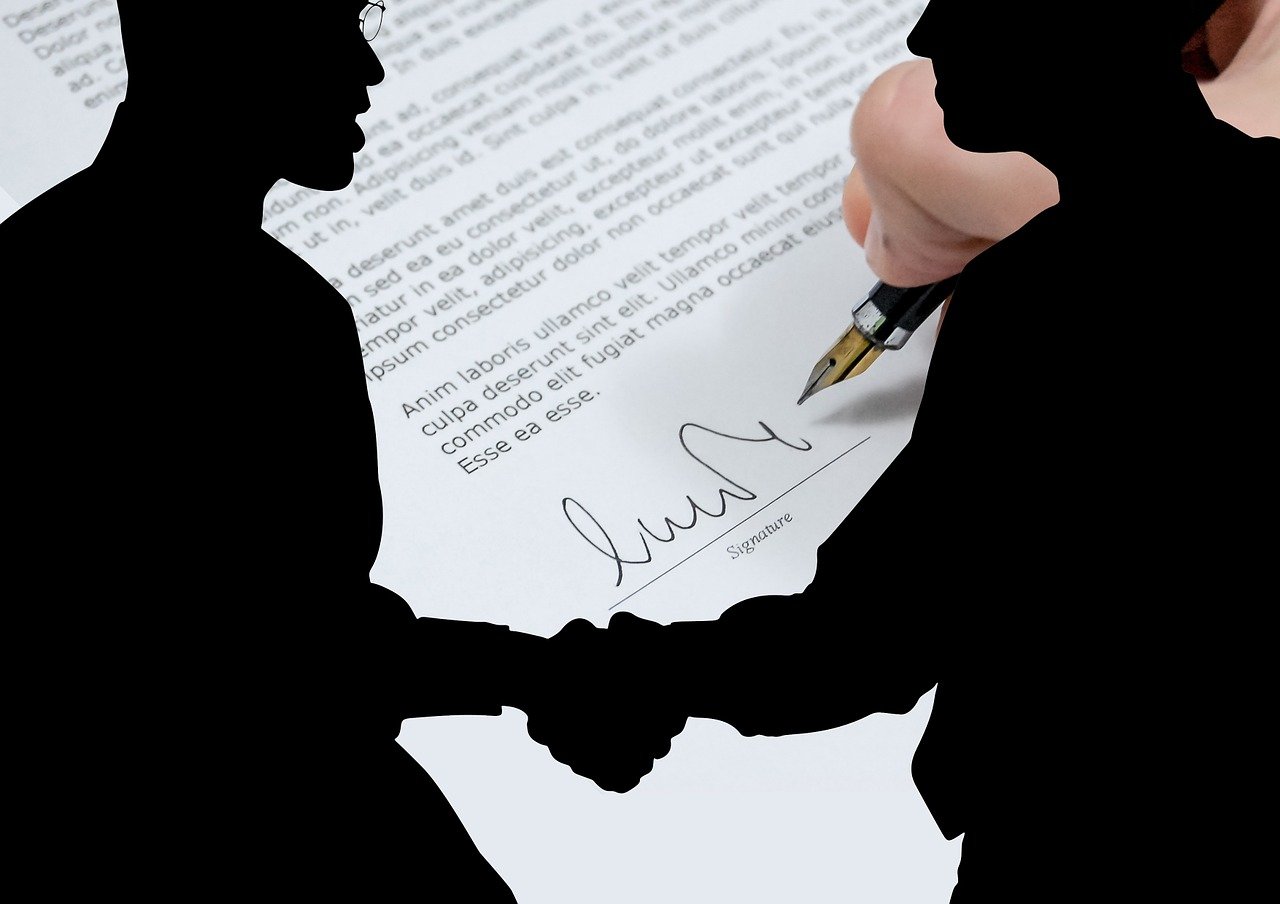
ジュビリーエースでは巧妙かつ多面的な勧誘手口が用いられていました。主な手口は以下の通りです。
7.1. 全国セミナーとオンライン勧誘
運営グループは全国主要都市で説明会やセミナーを開催し、大勢の参加者を集めて勧誘しました。大学生や社会人など幅広い層が対象で、講演者(関係者)が「最新のAI投資テクノロジーによる安定収益」などと熱弁し勧誘しました。またZoom等を使ったオンラインセミナーや勉強会も頻繁に行われました。
7.2. SNSや友人ネットワークの活用
若者層にはInstagramやTwitterなどSNSが勧誘窓口として使われました。実際に22歳女性Aさんの場合、大学の同級生がInstagramのストーリーで「投資に興味ある?」とアンケートを投げかけ、興味を示した彼女にダイレクトメッセージで接触しています。その後LINEに誘導し、「早く始めた方がいいよ」と親身な口調で勧誘するなど、知人の信頼関係を利用したアプローチが取られました。SNS上で投資家を名乗る他人から誘われたケースもあり、知らない相手でも「フレンドリーに教えてくれる先輩投資家」として信じ込ませる手口も確認されています。
7.3. マルチ商法的な紹介制度
出資者が新たな参加者を紹介すれば紹介料(コミッション)が得られるというマルチレベルマーケティング(MLM)の仕組みが導入されていました。具体的には、自分の紹介で誰かが出資すると、その出資額や配当の一定割合がボーナスとして紹介者に支払われる制度です。これにより出資者自身が勧誘者となって家族や友人を誘い込み、爆発的にネットワークが拡大しました。紹介者にはランク制度も設けられ、契約額や紹介人数に応じて最大5%の「アービトラージボーナス」が下位会員の収益から得られる仕組みだったと言われています。このように被害者を加害者に仕立てる連鎖により、勧誘の手は雪だるま式に広がりました。
7.4. 豪華な演出と権威づけ
勧誘の現場では、投資話を信じ込ませるための豪華な演出も行われました。例えば沖縄県内のセミナー会場には、1階のガラス張り部屋にジュビリーエースのロゴが入った高級車フェラーリが展示されていたとの証言があります。高級外車や一流ホテルでのパーティー、ハワイやマカオでの国際イベント開催など、「成功者」や「グローバル企業」のイメージを醸成する演出で参加者の心を掴みました。また主催者側は「著名人とも交流がある」「海外政府機関とも提携している」などと権威をほのめかす発言も行い、信頼感を高める戦術を取っています(実際に玉井容疑者は勧誘の場で「有名女優の○○と知り合いだ」と吹聴していたとの証言もあります)。
7.5. テクノロジーの見せかけ
勧誘説明では、「AIによる自動売買システム」が強調されました。ある被害男性は、勧誘者からパソコン画面にリアルタイムの仮想通貨取引と利益計上の様子を見せられ、「これが当社のAQUAシステムです。人間より正確に儲けます」と説明されたと証言しています。まるで本当に自動でお金が増えていくかのようなデモンストレーションを見せ、専門知識のない参加者を感嘆させました。また「出資直後に実際に1万円分だけ利確して現金化してみせる」といった試供品的な配当支払いも行われ、一度現金を手にした参加者は「本当に儲かるんだ」と安心してしまいました。
7.6. 勧誘時の嘘と安心材料
勧誘段階で参加希望者が不安を見せると、巧みなトークでフォローする手口も明らかになっています。Aさんが「これっていわゆるマルチ商法では?」とLINEで質問した際、勧誘担当の男は即座に「マルチとかねずみ講ではないです」と否定しました。さらに「何もしなくてもお金が増える投資です」「紹介すればプラスアルファでさらに利益が出る」と、リスクがなくメリットしかないように強調しています。また「大手保険会社が元本保証しているから安全」、「日本の法律上、仮想通貨だから問題ない」などと、疑問を持たれそうな点には都合の良い説明や嘘を重ね、安心させて契約を急がせました。
以上のように、ジュビリーエースの勧誘手口は人間心理を突いた周到な戦略でした。信頼できる知人からの誘い、高級感あふれる演出、もっともらしいテクノロジーの説明、そしてリスクゼロで高収益という謳い文句――これらが組み合わさり、多くの人々が疑いを抱かぬまま契約してしまったのです。
8. 勧誘・販売に関与した主な団体や人物・代理店

本事件の中心人物は、主犯格の玉井暁(たまい・あきら)です。玉井氏は東京都内在住の実業家で、事件当時53歳。「マルチ商法のカリスマ」「マルチの帝王」と異名を取る人物で、過去には健康ジュース販売のネットワークビジネスでトップセールスとなり年収2億円以上を稼いだ経歴を持ちます。玉井氏は派手好きでも知られ、FacebookなどSNSに海外リゾートでの豪遊写真を度々投稿し“成功者”ぶりをアピールしていました。しかしその裏で所得税約1億円を脱税して東京国税局に告発されるなど、法を軽視した金儲けに走っていた人物です。玉井氏は2019年頃からジュビリーエースの日本展開に深く関与し、日本各地のセミナーで講師役を務めるなど投資グループのリーダーとして君臨していました。「仮想通貨で集めれば無許可マルチでも金融商品取引法に触れない」と豪語し(実際には法改正でその抜け道は塞がれていた)、警察の摘発も高を括っていたと報じられています。結果的に玉井氏自身が2021年11月に逮捕・起訴され、2022年に有罪(執行猶予付き)の判決を受けました。
玉井氏の他にも、本件には複数の主要メンバーが関与しました。逮捕されたのは玉井氏を含め男女7人で、玉井氏の側近や地方で勧誘ネットワークを束ねていたリーダー格が含まれます。彼らは表向き「ジュビリーエース」や「ジェンコ」を名乗る投資運用会社の役員を称し、各自が自分の影響力のあるコミュニティで出資者集めに奔走していました。例えば大学生グループのリーダー、元教師の人脈を使った勧誘役、会社経営者層への勧誘役など、役割分担された代理店的存在があったとみられます。逮捕者以外にも、末端の紹介者ネットワークには膨大な人数が関わっており、結果的に被害者であると同時に加害行為(友人知人への勧誘)に関与してしまった人も多数存在します。
組織的には、「ジュビリーグループ」というゆるやかな組織体が全体を統括していたようです。海外拠点を標榜していたため法人登記上の正体は不明瞭ですが、玉井氏ら日本人メンバーが実質的に運営していたとされています。一方、公式サイト上ではトニー・ジャクソン(Tony Jackson)氏なる人物がCEOとして紹介されていました。ジャクソン氏は英国人風の名目上の代表で、2019年5月のマカオでのグローバル・ローンチイベントに姿を見せています。しかしこの人物は過去の実績が全く確認できず、おそらくは玉井氏らアジア人グループが用意した**表看板(お飾り社長)**に過ぎなかったとみられます。実質的な“胴元”は玉井氏を中心とするアジア(日本・香港・シンガポール等)のネットワークだった可能性が高いです。
また、関連団体としてはジュビリーエース崩壊後に登場した**「ジェンコ(JENCO)」社や「Globalytics Tech Research (GTR)」社があります。これらはジュビリーグループが名前を変えて立ち上げた後継スキームで、玉井氏のグループは出資者に対し「新しい運用会社に切り替える」と称してジュビリーエースからジェンコ、さらにGTRへと資金移動を誘導**しました。しかしこれらも同様に配当は出ず、最後には頓挫しています。ジェンコやGTR自体も幽霊会社であり、結局ジュビリーエースと同一グループによる詐欺的投資商品でした。
事件後、一部の関係者は懲りずに別の投資詐欺に関与しています。2023年に摘発されたマーケットピーク事件(ドバイ拠点を名乗る暗号資産投資勧誘)では、逮捕者の中にジュビリーエース事件に深く関与していた男Aが含まれていました。この男は玉井グループの中核メンバーだったとみられ、ジュビリーエース摘発後に新たな詐欺ビジネスに手を染めていたことになります。こうした動きからも、ジュビリーエース事件は特定個人だけでなく詐欺ネットワーク全体の問題であり、主要人物の摘発後もその周辺人物によって類似事件が繰り返されている実態が浮かび上がっています。
9. なぜ多くの人が信じてしまったのか – 手口と戦略
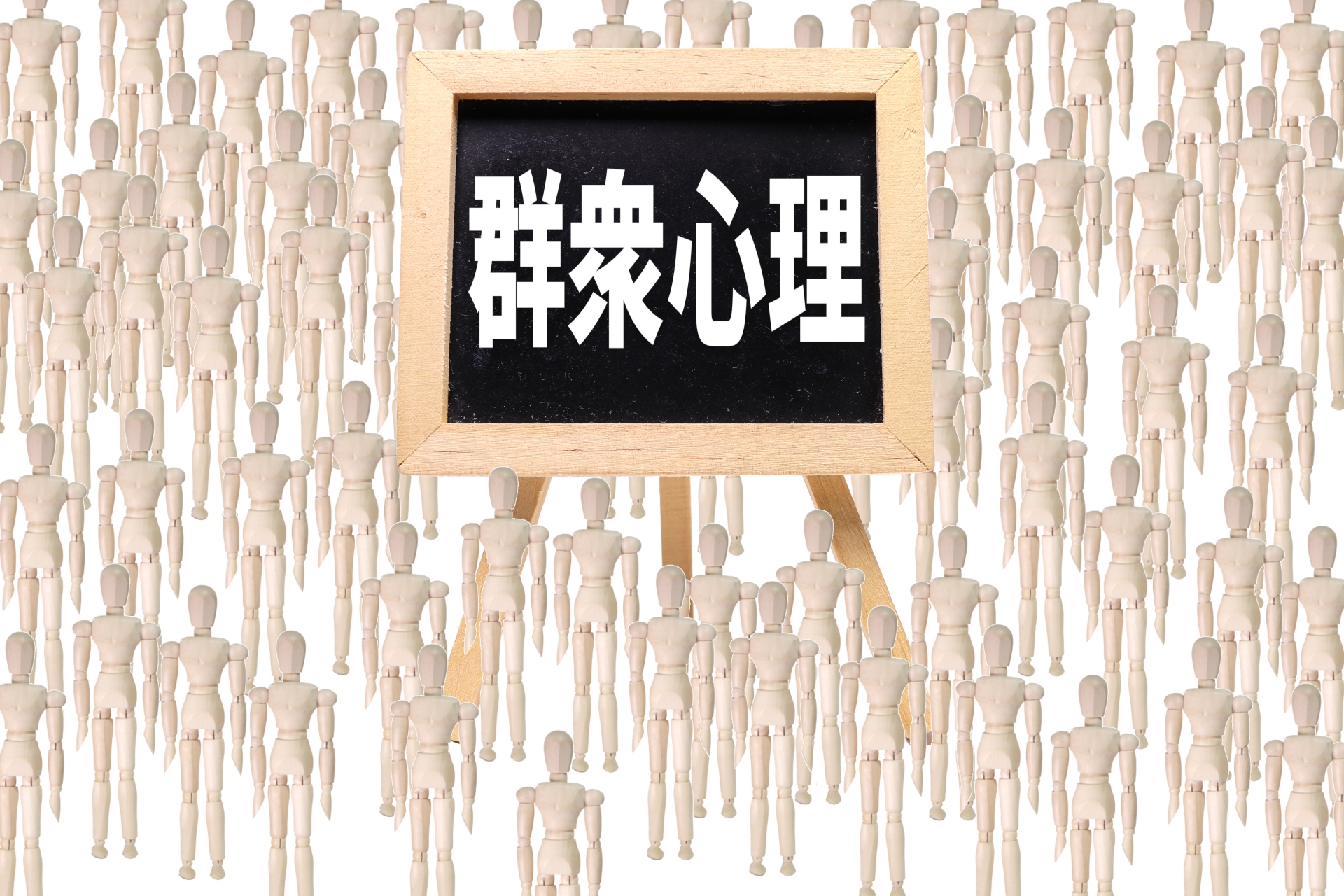
ジュビリーエースにこれほど多数の人々が騙された背景には、巧みな手口と心理戦略がありました。主な要因を以下に分析します。
9.1. 見分けの難しさ(リアルな投資との混同)
ジュビリーエースの勧誘話は、一見するともっともらしく感じられる点が厄介でした。暗号資産やアービトラージ取引といった実在の金融テクニックが盛り込まれ、一種の専門用語を駆使して説明されたため、投資初心者にはそれが合法で儲かる話なのか詐欺なのかを判断しにくかったのです。仮想通貨には実際に大きな利益を上げる人も存在するため、「自分も億り人になれるかも」という期待を抱かせやすい土壌がありました。また、配当も当初は実際に口座に数字が増える形で示されたため、架空ではないように見えたことも信用を高めました。結果として、多くの参加者は「怪しい話かもしれないが、本当に儲かっている人もいるらしい」「自分も少額から試してみよう」と深く考えず参加してしまいました。
9.2. 身近な人物・有名人の影響
詐欺師側は、人々の信頼する対象を利用しました。勧誘者が友人や同僚といった顔見知りだった場合、「この人が言うなら大丈夫かも」と心理的ハードルが下がります。また「自分の知り合いも儲けている」「先月◯◯万円利益が出た人がいる」といった身近な成功例が示されると、「みんなやってるなら安心」という同調バイアスが働きます。さらには、著名人の存在をほのめかす戦略も使われました。勧誘資料に有名投資家や芸能人との写真が掲載されたり、「海外の王族も出資しているプロジェクト」と紹介されたりすることで、権威付けが行われました。実際には虚偽でも、そうした**ブランド名-dropping(権威利用)**によって疑いが薄まり、「そんなすごい人達が関わっているなら本物だろう」と錯覚してしまったのです。
9.3. 高利益と低リスクの誘惑
「毎月20%の利益」「元本保証」「紹介すればボーナス」といったあまりに魅力的な条件そのものが、人々の判断力を鈍らせました。通常の投資ではあり得ない好条件ですが、一度「本当にそれが可能かもしれない」と思わせてしまえば、人間はそれを失いたくない心理(FOMO=機会喪失への恐怖)に駆られます。「疑ってチャンスを逃すくらいなら、とりあえず信じてみよう」とリスクを軽視させる効果がありました。加えて、「今始めれば先行者利益が得られる」「定員があります」などと急がせる手口も使われ、冷静に調べたり熟考したりする余裕を与えませんでした。結果、多くの人が正常な判断より欲望を優先して契約してしまったのです。
9.4. プロによる巧妙な説得
玉井氏らグループは詐欺勧誘のプロであり、相手の疑問や不安を解消する話術に長けていました。例えば「それって怪しくないですか?」と聞かれれば、事前に用意した実例(実際は虚偽のデータ)や専門的な説明で煙に巻きます。「出金停止になった」という事実にも「日本での金融ライセンス取得待ちで一時的に止まっているだけ」と尤もらしい理由を付けて正当化しました。さらに部分的な真実を織り交ぜたことも信用を高めました。仮想通貨の価格差取引自体は実在し理論上は利益が出ること、DeFi(分散型金融)などでは高利回りの商品も存在することなど、背景知識として本当の情報を織り交ぜつつ話を進めたため、話全体がリアルに感じられたのです。「全てが嘘」ではなく「ところどころ本当のことを言う」ことで、嘘の部分への疑念を和らげるという高度な話法でした。
9.5. 小額からの誘導と雪だるま式拡大
さらに、多くの人が少額から参加し、その後深みにハマっていった構図もあります。最初は「1口10万円からできる」とハードルを低く設定し、「ちょっと試してみよう」という気軽さでエントリーさせました。実際に口座画面で増える数字を見たり、少額の出金に成功したりすると安心し、「もっと増やそう」と追加投資してしまいます。また、自分が出資者になると紹介制度によって友人知人にも声を掛け始め、ネットワークが拡大しました。こうして自発的な勧誘連鎖が生まれ、疑いの声よりも「これは稼げる」という口コミが先行して広まっていったのです。多くの人が信じている状態そのものが疑念を打ち消す空気となり、被害が一気に拡大しました。
以上のように、ジュビリーエースの詐欺師たちは人間の心理的弱点(欲深さ、権威への弱さ、同調傾向、不安)を巧みに突き、技術や実績を装って信用させる戦略を取っていました。そのため投資経験の浅い若者だけでなく、ある程度知識のある社会人や主婦、高齢者までもが「自分だけは大丈夫」「今回は本物かも」と信じ込まされ、結果として日本全国でこれだけ多くの人々が騙されてしまったのです。
10. 今後の未来予測

ジュビリーエース事件は終息しましたが、同種の投資詐欺は今後も形を変えて現れる可能性が高いと専門家は指摘しています。実際、本事件に関与した人物が別の暗号資産投資詐欺(マーケットピーク)に再び関与し逮捕されるなど、詐欺グループは看板を掛け替えて活動を続けています。玉井被告自身、執行猶予付きとはいえ有罪判決を受け自由の身であり、「刑が軽いため既に次のターゲットを狙っているに違いない」とも報じられています。このように、詐欺ネットワークはしぶとく存続し得るため、今後も新たな名前・新たな手法で高利回りを謳う投資話が出てくると予想されます。
手口の高度化も予想されます。昨今はDeFi(分散型金融)やNFT、Web3といった新技術をうたい文句にした投資案件が増えており、詐欺師たちはこれら最新の流行語を利用してさらに巧妙な話を作るでしょう。例えば「〇〇トークンをステーキングするだけで年利◯◯%」「AIが自動運用するDAOプロジェクト」など、一見もっともらしいが実態のない案件が現れる可能性があります。ジュビリーエースのように国際色を出し、「拠点はドバイにある」「有名取引所と提携」などと言って日本の捜査網を掻い潜ろうとする動きも考えられます。実際、マーケットピーク事件では拠点を海外に置きつつ国内で無登録勧誘しており、ジュビリーエースと酷似した構図でした。
一方で、当局の監視と法整備は強化されていくでしょう。ジュビリーエース摘発は全国初の暗号資産による無登録ファンド摘発例となり、警察や金融当局も本格的に取り締まりに乗り出しました。金融商品取引法も暗号資産を規制対象に含めた改正が行われ(2019年改正・2020年施行)、法の抜け穴は塞がれています。今後、類似の無登録勧誘が発生すれば速やかに行政警告や摘発が行われる可能性が高く、詐欺グループにとっては活動しにくい環境になりつつあります。また、消費者庁や警察は若者向けに投資詐欺の注意喚起を強めています(高校・大学での啓発講座やパンフレット配布など)。被害者側でもSNS等で情報共有する動きが活発化し、一度詐欺の手口が知れ渡ればそのスキームは急速に信用を失う傾向もあります。
総合すると、**「第二、第三のジュビリーエース事件」**が起こるリスクは依然残るものの、社会の警戒感は高まりつつあります。詐欺グループはより巧妙に潜伏する一方、当局の摘発スピードも上がり被害拡大前に露見するケースが増えるかもしれません。ただし騙す側が完全にいなくなることは考えにくいため、今後も**個人レベルで警戒を怠らず、怪しい案件に近づかないこと**が求められるでしょう(詳細は「今後の予防策」に後述)。
11. 返金の可能性

出資金の返金(被害回復)の可能性は極めて低いのが現状です。警察の捜査で押収された現金等はごく一部(約2億円)に過ぎず、集められた暗号資産の大半は既に運営側から流出済みと見られています。警視庁関係者も「集めた仮想通貨は流出しており、出資者への返金は厳しい状況
警視庁関係者も「集めた仮想通貨は流出しており、出資者への返金は厳しい状況」とコメントしており、被害額650億円の回収は絶望的です。
刑事裁判においても、金融商品取引法違反での有罪判決となったため加害者に被害弁償命令等は出ていません(詐欺罪での立件ではないため、直接の返金義務は判決に含まれず)。玉井被告らに科されたのは執行猶予付きの懲役刑とおそらく罰金程度で、被害者への補償は刑事上期待できません。
そのため被害者側は民事訴訟や和解交渉による回収を試みています。実際に前述の22歳女性の遺族は勧誘者らに対し約1,265万円の損害賠償を求め東京地裁に提訴しました。他にも、数千万円規模を失った男性が玉井被告ら主要メンバーを相手取り出資金返還を求める民事訴訟を起こしています。これらは加害者個人の責任を追及して少しでも返金させようという動きですが、仮に勝訴判決を得ても実際に回収できるかは不透明です。玉井被告らは資産を海外に移したり浪費したりしており、残存資産がほとんど無い可能性が高いためです。税務当局が差し押さえた2億円も、まずは滞納税(金)に充当されており被害者には直接戻りません。
一方、末端の勧誘者に対する損害賠償請求も行われています。友人知人を騙して出資させた勧誘者には民事上の不法行為責任が問われ得るため、被害者の中には「あなたの紹介で損害を被った」として知人に賠償請求するケースも出ています。もっとも、勧誘者自身も被害者であることが多く、賠償資力が乏しい場合がほとんどです。実際に遺族が提訴した同級生らも若年層であり、大金を支払える見込みは不明です。
以上のように、現実的な返金は困難なのが実態です。警察・検察としても刑事罰を科すことで精一杯で、金銭被害の救済までは手が届いていません。国の被害者救済制度(詐欺被害は対象外)も無いため、公的支援も期待できません。被害者は各自で泣き寝入りするか、加害者を民事で訴えて僅かな回収を目指すしかない状況です。消費者センター等では「決して諦めず相談を」と呼びかけていますが、現時点で出資金が全額戻った例は確認されていません。
今後、玉井被告らが保有していた海外資産などが新たに見つかれば差押え・返還に充てられる可能性もゼロではありませんが、期待は薄いでしょう。被害に遭ってしまった後では取り返しがつかない――この事実もまた、本事件が残した厳しい教訓の一つです。
12. 最初から詐欺だったのか?

結論から言えば、ジュビリーエースは最初から詐欺的性格を持った投資プログラムだったと考えられます。その根拠はいくつもあります。
まず、事業の基本スキーム自体が典型的なポンジ・スキームの構造でした。運営開始当初から法定利息では考えられない月利10~20%という高配当を約束し、しかも元本保証まで付けるという常識外れの条件を提示していました。健全な金融商品であれば、そんな条件は通常あり得ず、それ自体が詐欺の強い疑いを帯びるものです。また、金融庁などへの登録を一切行わずに巨額の出資を集めていた点も、正規ビジネスではなく違法行為を前提としていたことを示します。
次に、運営者側の行動も初めから詐欺師そのものでした。玉井氏らは当局の目を逃れるために会社名義を偽装したり(虚偽登記の会社口座を利用)、領収書を出さず証拠を残さない徹底ぶりでした。さらに集めた資金を本来の運用目的に使わず、自分たちの豪遊や蓄財に充てていた形跡があります。玉井氏の未申告所得24億円という事実は、まさに出資金を私的に流用していた裏付けと言えます。本当に投資運用を行う気があれば、出資金は事業に回されるはずで、個人の所得がそこまで跳ね上がることはありません。最初から出資金=自分たちの儲けと考えていた可能性が高いのです。
また、計画倒産的な段取りも見られました。ジュビリーエースで十分に資金を集めると、早い段階でジェンコやGTRなど新ブランドへ移行しています。これはポンジ・スキームで資金繰りが行き詰まるタイミングに合わせて、別名義で再度資金を集め直そうとする常套手段です。実際、ある男性はジュビリーエースに110万円出資した後「新しいシステム」に230万円を追加出資させられましたが、どちらも配当はほぼゼロだったと証言しています。最初から最後まで、一貫して出資金をだまし取ることだけが目的だったことが窺えます。
さらに、ビジネスモデルの不自然さも挙げられます。アービトラージ取引自体は理論上可能ですが、世界中の取引所の価格差を常時発見して自動売買するのは高度な技術と莫大な資本が必要です。ジュビリーエースはそれを可能にすると称しましたが、外部に対して一切の検証可能なデータを示していません。法定監査も受けず財務報告も皆無で、実際に取引でいくら利益が出たかの開示もありませんでした。まともな金融ビジネスであれば考えられない不透明さです。裏を返せば、開示すればボロが出る(実際には運用していない)ため、初めから隠し通す前提だったと推測できます。
こうした状況証拠から、ジュビリーエースは当初から投資ビジネスを装った詐欺計画だったと言えます。表面的には仮想通貨ブームに乗じた新ビジネスの顔をしていましたが、その実態は従来からあるねずみ講型詐欺を最新の流行用語で包装したに過ぎません。したがって「途中で方針転換して詐欺になった」のではなく、「最初から詐欺として企てられた」ものと考えるのが自然でしょう。警視庁が押収物や資金流れを調べた上で摘発に踏み切った点から見ても、運営側に善意は一切なく、端緒から詐欺行為だったことは疑いようがありません。
13. 今後の予防策

ジュビリーエースのような投資詐欺に二度と騙されないための予防策をまとめます。本事件の教訓を踏まえ、以下のポイントに注意することが重要です。
13.1. 金融業者の登録確認
投資話を持ちかけられたら、まずその事業者が金融庁または都道府県に適切に登録・許可されているか確認しましょう。日本で投資商品の勧誘を行うには金融商品取引業等の登録が必須であり、無登録業者との取引は違法かつ極めてリスクが高いと金融庁も警告しています。金融庁のウェブサイトには登録業者一覧や無登録業者の警告リストが公開されています。今回のケースでも、最初に「ジュビリーエースは金融庁未登録」と気付いていれば多くの人が踏みとどまれたはずです。業者名やサービス名で検索し、公式な登録情報や過去の行政処分歴がないか調べる習慣をつけましょう。
13.2. 「うますぎる話」は疑う
年利換算で100%以上など、常識外れの高利回りをうたう投資話はまず詐欺を疑うべきです。一般に無リスクで得られる利回り(無リスク金利)はごく低水準であり、年利数%でも高い部類です。それを大幅に超える利益を「確実に」「保証付きで」などと言う案件は99%詐欺と考えて差し支えありません。加えて「誰でも簡単に何もしなくても儲かる」といった甘い言葉が並ぶ場合も要注意です。投資は元本割れや損失リスクと隣り合わせであるのが常識で、リスクゼロを強調する商品など本来あり得ません。今回の詐欺でも「元本保証」「放置で増える」と宣伝されていましたが、これらは典型的な勧誘トークです。「おかしい」と少しでも感じたら契約しない勇気を持ちましょう。
13.3. 第三者の意見を求める
儲け話を持ち掛けられると冷静さを欠いてしまうものです。判断に迷った時は、信頼できる第三者(家族、専門家など)に相談しましょう。自分一人で決めず、他の人の目から見ても妥当な話か確認することが大切です。消費者センターや警察の相談窓口(#9110 等)では、怪しい投資案件かどうかアドバイスを受けることができます。特に若い方は周囲に経験豊富な人がいれば意見を仰ぎましょう。今回は大学生同士で閉じたコミュニティ内勧誘が行われ、外部の大人に相談せず契約してしまった例が多く見られました。「人に話せないような投資はするな」という鉄則があります。少しでも不安があれば専門機関に相談し、自分だけで抱え込まないことです。
13.4. 資料や契約書の有無を確認
正規の金融商品であれば必ず契約書や目論見書、重要事項説明書などが交付されます。口頭やLINEのやり取りだけで契約を急がせるような案件は非常に危険です。領収書や契約書を出さない場合は、後で証拠を残さない意図が疑われます。出資する前に必ず書面を要求し、それを持ち帰って熟読しましょう。書面交付を渋る業者はアウトと考えてよいです。また契約書類があっても専門用語だらけで意味が不明な場合があります。その際も安易に署名捺印せず、理解できるまで質問するか専門家に見てもらうべきです。
13.5. 少額テストと引き際を決める
どうしても興味を持ってしまった場合でも、一度に大金を投入しないことです。最初から借金してまで多額を投じるのは論外で、やるとしても損失を覚悟できる極めて少額に留めるべきです。さらに、「少しでも不審な点(配当遅延など)が生じたら即座に撤退する」といったマイルールを決めておくことも重要です。詐欺案件では初期に少額出金できても徐々に引き延ばされ、ずるずると追加投資させられるケースが多いです。欲を出さず、当初の約束が1つでも守られなければスパッと手を引く決断力が被害拡大を防ぎます。
13.6. マルチ勧誘への警戒
投資話で「友人紹介するとボーナス」などネットワークビジネスの要素が出てきたら要警戒です。純粋な投資であれば紹介料ビジネスは本来不要であり、紹介マージンで人集めをしなければ成り立たない時点で怪しむべきです。友人から誘われた場合でも、「紹介すると儲かるらしい」という話なら一旦疑いましょう。大事な友情や信用を失うリスクもあります。実際、本事件では紹介した側も加害者になってしまい、人間関係が崩壊した例もあります。マルチと投資の組み合わせは非常に危険なサインとして覚えておきましょう。
13.7. 金融リテラシーの向上
最終的な自衛策は、自身の金融知識を高めることです。仮想通貨や投資の基本を正しく理解していれば、詐欺の荒唐無稽さに気付きやすくなります。「年利○%」「複利運用」「元本保証」など用語の意味や実現可能性を知っていれば、過剰な謳い文句に惑わされずに済みます。近年、若年層の投資被害が増えている背景には金融リテラシー不足が指摘されています。学校教育や自己学習でお金の基礎を学ぶことが、詐欺に騙されない土台となります。怪しい話に触れたら良い勉強機会と捉え、ぜひ一度冷静にその仕組みを調べてみてください。
以上の対策を心がけることで、ジュビリーエースのような巧妙な投資詐欺から身を守る可能性が高まります。特に暗号資産分野は新しく難解なため詐欺師に付け込まれやすい側面がありますが、基本に立ち返れば「楽に大儲けできる話など存在しない」という真理は昔も今も同じです。今回の事件の惨状を他山の石とし、高利回りの誘惑に惑わされない冷静さと情報を見極める目を養うことが何よりの予防策と言えるでしょう。
参考資料: 本レポートは、警察発表や報道記事、被害者証言、法律専門家の解説等をもとに客観的事実を整理したものです。詳しくは各出典をご参照ください。
参考文献
- 文春オンライン「前田敦子から昨日電話があった」「優木まおみと食事したことがある」… 650億円を集めて逮捕の“マルチ商法ビジネスのドン”の怪しい謳い文句
- JC-NET(ジェイシーネット)「仮想通貨投資勧誘で650億円「ジュビリー」7人逮捕 「ジュビリーエース」「ジェンコ」 - 全国情報-政治経済・時事・倒産情報」
- 先物取引被害の相談窓口「ジュビリーグループ 無登録 650億円相当集金か」
- JinaCoin「仮想通貨のHYIP(ハイプ)案件とは?高利回り投資詐欺!?絶対手を出すな」
- All About「若者を食い荒らした凶悪詐欺事件、なぜ被害は拡大したのか? [暮らしのお金] 」
- CO2排出権取引・仮想通貨 被害相談「ジュビリーグループ 無登録 650億円相当集金か」
- 金融庁「無登録業者との取引は要注意!! ~無登録業者との取引は高リスク」
- 高校生・大学生必見!! 金融トラブルの今 ~投資詐欺編 - note
よくある質問(FAQ)
Q1: ジュビリーエースは完全に違法な詐欺だったのですか?
A1: はい。ジュビリーエースは、日本の金融商品取引法に基づく登録を一切行わずに投資勧誘を行っていました。これは明確な違法行為です。また、謳っていた高配当や元本保証も虚偽であり、実態はポンジ・スキーム(ねずみ講)であったことが捜査で明らかになっています。
Q2: 勧誘してきた友人や知人も訴えるべきですか?
A2: 友人や知人が故意に詐欺に加担していた場合、民事上の損害賠償責任を問える可能性があります。しかし、彼ら自身も被害者である場合が多く、賠償能力がないことも考えられます。まずは弁護士に相談し、法的なアドバイスを受けることをお勧めします。
Q3: 支払ってしまったお金は戻ってきますか?
A3: 残念ながら、返金の可能性は極めて低いのが現状です。集められた資金の大部分は既に海外に流出しており、回収は困難です。民事訴訟を起こすこともできますが、勝訴しても実際に回収できるかどうかは保証できません。
Q4: 今後、同様の詐欺に遭わないためにはどうすればいいですか?
A4: 本記事で紹介した予防策(「13. 今後の予防策」参照)を参考にしてください。特に、
- 「うますぎる話」は疑う
- 金融庁の登録業者か確認する
- 契約前に必ず第三者に相談する
の3点は必ず守るようにしましょう。
Q5: 仮想通貨への投資はすべて危険なのですか?
A5: いいえ。仮想通貨自体は、新しい技術であり、将来性のある投資対象となる可能性もあります。しかし、仮想通貨に関連する詐欺が多いことも事実です。投資する際は、信頼できる情報を収集し、リスクを十分に理解した上で行うようにしましょう。金融庁に登録された交換業者を利用するようにしましょう。
この記事が、ジュビリーエース事件の理解と、今後の投資詐欺被害防止の一助となれば幸いです。
あなたの声を聞かせてください!
感想・リクエスト・タレコミ、大歓迎!
下の送信ボタンから、あなたの意見をぜひお寄せください。
🎁 今ならもれなく3大プレゼント! 🎁
- 💡 「最新詐欺手口&対策リスト(2025年版)」
👉 急増する詐欺の手口と回避策を、わかりやすく解説! - 💰 「知らなきゃ損!政府の補助金&助成金リスト」
👉 住宅・子育て・医療・教育…今すぐ使えるお金をチェック! - 🏦 「銀行・クレジットカードの隠れ手数料一覧」
👉 知らずに払ってる手数料、サクッと削減する方法を伝授!
👇 あなたの一言が、新たな情報発信のヒントに!
今すぐ送信して、プレゼントをGET🎁✨
